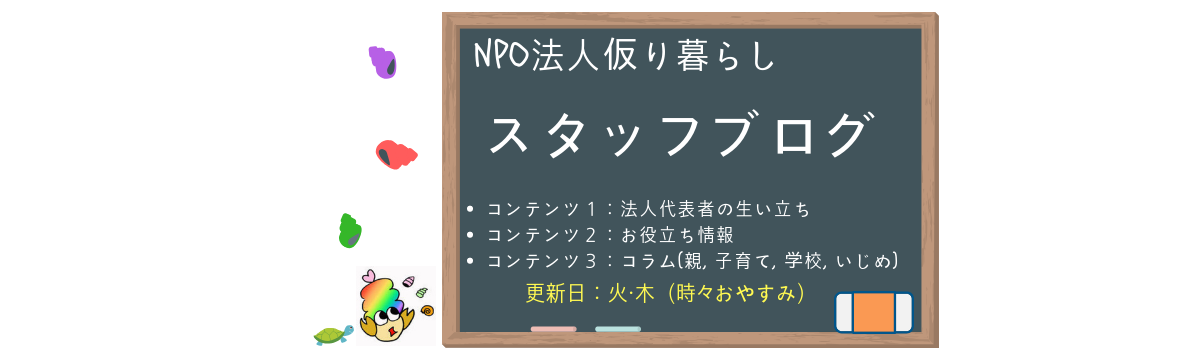こんにちは、NPO法人仮り暮らし代表の徳永です。
このコラムではなるべく素の私を出していこうと思います(いかに猫かぶってるかバレバレです)。
*今後のMTG次第では変わるかも。
今回は山本五十六の「やってみせ」を体現してみせた2人のお母様をご紹介します。
悪いお手本

幼稚園の年長さんくらいの男の子と、赤ん坊を乗せたベビーカーを押す推定20代後半のお母ちゃんというご一行です。
駅の改札機の中で、男の子がSuicaを持ってました。ピッとやりたかったのかな、それとも社会勉強でしょうか。その子は改札機の入り口でウロウロ。次々に人がやってきて詰まる改札。焦るお母さん。
お母さん、唐突にその子の頭を顔が傾くくらい強くばしっとはたいて、「あーもう早く!そこ!」と言い放ちました。
男の子、泣かずに真顔でピッとタッチし、改札を通過。改札の詰まりも解消。でも、その時の男の子の表情が切なかった。しょぼーん、どころか感情そのものが無かった。
見てて 胸 糞 悪 か っ た です。言葉が悪くてすみません。
子どもと満足な意思疎通もできないのに、そんなもんやらすなよ。

このシーン、母親がSuicaを持って通ればよかっただけですよね。別に手がふさがっていたわけでもなし。男の子が怒られる、ましてや叩かれる必要はどこにもありません。そもそも子どもなんだから、できなくて当たり前なんです。
男の子のSuicaタッチの練習というのなら、それこそ人の少ない時間帯・改札を選んでやるべきであって、1人の失敗で改札が詰まるような状況でやらせるべきではない。
それができないのなら、あらかじめ「青いところにタッチしてね」とか、「ここ(と指差して)にタッチしてね」と言っておけば通じるはずです。男の子は危なげなく二足歩行してるんだから。
いくら赤ん坊連れだからといって、男の子に乱暴になる理由にはなりません。子ども2人も連れてると、イラっとするのも分からないでもないけれど。
どうして改札機の入り口でウロウロしてたのか?
やり方が分からなかったのか?
やり方は分かっていたけど、タッチしていいのかどうか不安だった?
すべてを察して先回りしろとは言いませんが、このシーンだったら事前に教えてあげてれば防げたはずです。この男の子はきっと、Suicaでの改札入退場の仕組みを理解できるまでは毎回怯えるでしょう。
お母さんも怖い、改札機も怖い。リラックスしてチャレンジできない。身構えるから失敗する。また怒られる。成功体験ができない、自己肯定感が育たない。
お母さんとしては、改札は詰まるし(男の子がタッチしてくれないから)、先に進むこともできないし、周囲の人間からは睨まれるし で焦ったんだとは思いますが、それにしたってやり方、言い方、教え方ってもんがあると思うのです。
子どもが失敗する。周りに迷惑がかかる。子どもの失敗を怒る。周りから「何?あれ」という視線で見られる。悪循環です。
良いお手本

別の日に、こちらは4,5歳くらいの女の子を連れたお母さん。同じく駅の改札でSuicaを幼女に持たせて通過しようとしていました。改札もすべての改札にまんべんなく人が通る状態です。
「ここよ、ここ。ここね、タッチしてね。」
ピッ
「ハイありがとー。進んで進んでー。はいカードちょうだい。上手にできたねー^^」
ピッ
「ハイありがとー。進んで進んでー。はいカードちょうだい。上手にできたねー^^」
女の子、にこっとはにかんで得意顔。見てて感動して泣きそうになりました。これが「子どもに教える態度」だと思うんですよね。
具体的にやり方を教えて、その通りにできたらほめる。
お母さんが普段からこういう教え方だから、子どもはリラックスしてお母さんの言うことを聞くことができ、物事にチャレンジできる。だからすいすい上手く行く。成功体験ができる。自己肯定感が育まれる。失敗しても怖くない。だから身構えなくてよい。
お母さんとしても、子どもはどんどん新しいことを覚えてくれる。怒らなくていい。周りから「何?あの人」な視線を受けないですむ。むしろ「あぁ、こんなお母さんイイナ」な視線。子どもからも好かれる。好循環ですね。
ほめて育てるとは
子どもにものを教える時はできるまで待つ、できたら褒める。自分のことも褒める。ぜひやってみてください。いつも子どものこと叩いてるわーというお母さんお父さんは、今すぐ保健所のカウンセラーさんに相談してください。大げさに言ってるわけではありませんよ。
ちなみに、ほめて育てるっていうのは、「ちゃんとできたら」ほめるんですよ。
なんか勘違いしてる親御さんたくさんいらっしゃいますけど、例えばいじめっ子に対して「んまぁー坊ちゃんは強いわねー」とか、「自分の意見を持ってるのよねー」とかいう、何でもかんでも褒めりゃいいってもんじゃないですよ。
ご意見・ご質問・記事リクエストは仮り暮らしHPまで!